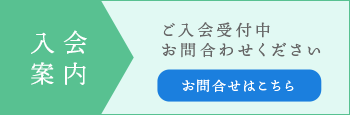「貫く企業理念」編はこちら
「100年経営の道」編はこちら
「絆」編はこちら
-
キハラ
-
[2025年4月7日]
地震に負けない図書館作る
図書館用設備・用品のキハラ(東京都千代田区、木原一雄社長)は創立110周年を迎えた。地域振興や人々が触れ合う場づくりを各図書館が進める中で、減震技術や除菌ボックスの投入などにも力を入れる。“良きパートナー”として「図書館を元気にし、日本で一番お客から喜ばれる数の多い会社にするのが夢」(木原社長)という。
続きを読む
-
[2025年4月7日]
-
第一滝本館
-
[2025年3月31日]
老舗が挑むSDGs
第一滝本館(北海道登別市、南智子社長)の起源は1858年(安政5)に開祖の滝本金蔵が病気の妻のために開湯した「愛妻の湯」にある。名湯として名高い登別温泉の湯元として今でも北海道の観光産業の中心にあるとも言える。その湯と「おもてなしの心」は安政の昔と変わらず世界中の人々を癒やし続けている。
続きを読む
-
[2025年3月31日]
-
小松電気化学工業
-
[2025年3月24日]
多能工化でメッキ短納期
小松電気化学工業(石川県小松市)は、職業軍人だった西登喜雄氏が1953年(昭28)に稲荷めっき工業所として創業した。早くから地元のコマツと取引があり、建設機械や産業機械用大型部品の硬質クロムメッキを得意とする。他にも亜鉛やニッケルの電気メッキなども手がけており、多品種少量品から量産品まで対応できる。
続きを読む
-
[2025年3月24日]
-
アピ
-
[2025年3月17日]
蜂蜜通じて健康社会創る
アピ(岐阜市、野々垣孝彦社長)の祖業は養蜂だ。16歳の野々垣良三氏が1907年(明40)に兄と創業し、養蜂器具も製造販売した。24年に独立し会社を設立。当時の先端ビジネスだった養蜂を陰で支えた事業は健康補助食品や医薬品を受託生産する今に通じる。
続きを読む
-
[2025年3月17日]
-
小林製作所
-
[2025年3月3日]
自主性尊重、発展目指す
小林製作所(石川県白山市)は、刀鍛冶の家系を持つ初代の小林賰三氏が1919年(大8)に創業。当初は織機や軍艦などのボルト、ナットを製造していた。後年、大量生産の失敗やオイルショックなどの苦難を乗り越え、精密板金加工にシフトして大きく成長した。
続きを読む
-
[2025年3月3日]
-
アース製薬
-
[2025年2月24日]
感染予防、人に寄り添う
アース製薬は2025年、設立100年目を迎える。1892年(明25)に大阪難波で木村秀蔵氏が創業し、1925年(大14)に前身となる木村製薬所を設立した。アース製薬に社名を変えたのは64年(昭39)だ。虫ケア用品「ごきぶりホイホイ」「アースノーマット」、入浴剤「バスロマン」などロングセラーとなる商品を生み出してきた。
続きを読む
-
[2025年2月24日]
-
西村黒鉛
-
[2025年2月17日]
西村黒鉛(大阪市淀川区、西村悟志社長)は、乾電池用材料のマンガンや黒鉛を販売する商社「西村商店」として、1931年(昭6)に西村茂氏が創業した。現在は黒鉛加工や鋳造設備の販売代理店として事業展開する。黒鉛加工は鋳造業界向けを柱としているが、放熱性や導電性などの黒鉛の特徴を生かし、電子部品材料向けなど新たな用途開拓にも取り組む。
続きを読む
-
[2025年2月17日]
-
阪神電気鉄道
-
[2025年2月3日]
阪神電気鉄道は文字通り大阪と神戸を結ぶ大手私鉄で、2025年に営業運転開始120年を迎える伝統ある鉄道会社。頑丈な交通インフラを築き、車両冷房化や駅トイレの洋式化をいち早く進めるなど顧客志向できめ細かいサービスを展開する。プロ野球「阪神タイガース」とともに地元から愛される存在だ。
続きを読む
-
[2025年2月3日]
-
対松堂
-
[2025年1月27日]
対松堂(愛知県豊川市、林紫朗社長)はプリント基板の設計、実装が主力事業。社名から現在地を連想できないが、創業からの道のりは「その時々の主力事業の隣にある仕事を手がけてきたことにある」と田中寛孝会長は歴史をひもとく。 田中会長は5代目。江戸時代後期、現在の愛知県豊川市内の街道沿いの宿場町にあったよろず屋が2代目の時に店先の一部で生薬を取り扱った。3代目は薬種商を始めるにあたって店の前の松の木にあやかり「田中對松堂薬店」と命名した。
続きを読む
-
[2025年1月27日]
-
大七酒造
-
[2025年1月20日]
大七(だいしち)酒造(福島県二本松市、太田英晴社長)は、江戸時代中期から続く老舗酒蔵。昔ながらの「生酛(きもと)造り」を272年の間、受け継いできた。太田社長は「これほど長くこの製法を続けているのは全国でも当社くらい」と話す。伝統が息づく製法を守りつつ、味のさらなる向上や海外への販路拡大など同社の営みは“不変と革新”そのものだ。
続きを読む
-
[2025年1月20日]